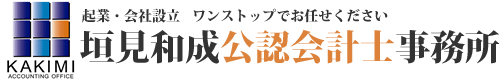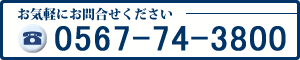��@�l�ƌo�c�҂̐ߐő�ɂ��ā�
��Ђ̐ߐő�͌o�c�҂Ȃ�N�ł�����ɂ߂���̂��Ǝv���܂��B�o���邾�����Ȃ��������ƁE�E�E�B�m���ɍ��̍��ɑ��Đŋ���[�߂Ă��K���Ɏg���Ă���Ƃ͓���v���Ȃ����߁A���������Ȃ��Ƃ����v���������Ǝv���܂��B�������A���{�ɂ����ẮA�@���ɏ]���Ĕ[�ł��邱�Ƃ͍����̋`���ƂȂ��Ă��܂��i���E�̒��ɂ͐ŋ���[�߂�K�v�̂Ȃ���������܂����E�E�E�j�B�o�c�҂̊F����������͊�����Ĕ[�ňӎ��������Ă������������Ǝv���܂��B�Ƃ͂����Ă��A���ʂȐŋ���[�߂�K�v�͂���܂���̂ŁA�l�X�Ȑߐł̕��@��������Ă��܂��B�ߐŌ��ʂ̍������@�͌��Z���O�ɂ����s���Ȃ����Ƃ������̂ŁA�������Z����������s���č������v���ǂ̂��炢�o�邩�����Z���O�܂łɂ�����x�c������K�v������܂��B���̐����ɂ��ߐŕ��@��I�����Ă����̂��ǂ��Ǝv���܂��B���Z�����߂��Ă��܂��ƁA�s���邱�Ƃ�����ꂠ�܂���ʂ�����܂���B���̏ꍇ�A�E�łɎ����߂Ă��܂��\��������܂��B
���̍l���ł����A���㍂��3���̐ŋ��͉�Љ^�c��̕K�v�o��Ǝv���Ă��܂��B�ŋ���[�߂�Ƃ������Ƃ͗��v���o�Ă��邱�Ƃƕ\����̂ł���A���v���o�����Ƃɂ���Ђ̗͑͂��t���Ă��܂��B�p���I�ɂ���3���̐ŋ���[�߂��Ђ͉i���I�ɔ��W���Ă�����Ђƍl���Ă��܂��̂ŁA����3���̐ŋ���[�߂��ЂɂȂ��Ă��������B
|
�V���ƔN�x�J�n�����2�����ȓ��ɍs���Ă�����������
|
���@������V�̊z�̌���
������V�͊��呍��̌��c�����̂��߁A�ʏ�A���Z������2�����ȓ��ɂ����Ȃ���莞���呍��Ō��肳��܂��B���̎��ɐV���ƔN�x�̗��v��\�����A������V�̊z�����肵�܂��B�܂������ɉƑ�������ɏA�C����������V���x�������Ƃ͏����U���邱�ƂɂȂ�A���Ȃ�̌��łɂȂ���܂��B
�i���j������V�̋��z�́A���ۂ̎d�����e�⓯�Ǝ�̏Ɣ�r���ē��ɉߑ�ƂȂ�ꍇ�́A�����Ƃ��ĔF�߂��܂���̂Œ��ӂ��K�v�ł��B���ڂ��������ɂ��ĉߑ�Ȗ�����V���x�������Ƃ͐Ŗ���F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�܂��A������V�͈�x���肵�����z�͓��ʂȏ̕ω����Ȃ�����1�N�ԓ��z�łȂ���Ȃ�܂���B���ʂȏ̕ω��Ƃ́A�@���炩�ȋƐш����ɂ���V�̌��z�A������������\������В��ȂǑ啝�ȐE���̕ω��ȂǁB
���ЂɑސE�����x������ꍇ�A�ސE���Ɉꊇ���đސE�����x�����Ǝ����I�ɂ����v�I�ɂ����S���傫���Ȃ�܂��B���̂��߂ɁA������ƑސE�����ςւ̉����������߂��܂��B
�����b�g�F�����[�t����K�v������܂����A�S�z�o��Ƃ��ĔF�߂��܂��B�O���ϗ��̂��ߑސE�����m�ۂ��Ă������Ƃ��\�ƂȂ�܂��B
�f�����b�g�F�������O���ɗ��o���܂��B�܂��A�{�l�ɂ������t������܂���̂ŁA�������ق̏ꍇ�ł��{�l�Ɏx�����A����Ƃ��A���������I��������܂���B��Ђɋ��t�������@�Ƃ��āA���Q�ی����̊��p������܂����A�����܂ŕی��̂��ߎx�������ی����ȏ�̉��Ԗߋ��͂���܂���B
�@�@�@ ↓
������x����I�ɗ��v���o���Ђ͉����������߂��Ă���܂��B�ʏ�A���ȓs���ސE�Ŏx�������ސE�����J�o�[�����悤�Ɋ|������ݒ肵�܂��B�i�ꗥ�Ɋ|������ݒ肷�邱�Ƃ͖��ʂł���܂��j
|
���Z���܂łɍs���Ă�����������
|
�|�C���g�F���L�̓��e�͎x�o�������܂����A�s�K�v�Ȃ��̂△�ʂȂ��̂��w�����邱�Ƃɂ���āA�Ŋz�����Ȃ����Ă��Ӗ�������܂���B�K���K�v�Ȏ����ɂ��Ă̂ݍs���悤�ɂ��ĉ������B���̌��ʁA�Ŋz����������Ƃ������Ƃ͎��Ƃ������ł��邱�Ƃ̗��t���ƂȂ�܂��B
���@�C�U���̎��{
������@�B�̏C�U���K�v�ȏꍇ�A���Z���O�܂łɊ������܂��傤�B�����̏C�U�ɂ��āA�����̖h���H�����A�ʏ�s����C�U�͌���̕i���𖾂炩�ɍ��߂Ȃ����x�ł���A���z�̑��ǂɂ�炸�o��Ƃ��ĔF�߂��܂��B�@�B�ɂ��Ă��A���炩�ɋ@�\�����߂���ǂłȂ���A�o��Ƃ��ĔF�߂��܂��B���z�▾�炩�ɋ@�\�A�b�v���F�߂�����͎̂��{�I�x�o�̂��߁A���Y�v�シ��K�v������܂��B
�]�ƈ��ɑ��錤�C���[�������܂��傤�BOJT�ł��Ȃ�̌��C�����邱�Ƃ͉\�ł����A�O�����C�𗘗p���邱�Ƃ́AOJT�ł͈Ⴄ���_�ł̌��C�ƂȂ�܂��̂ŐϋɓI�Ɋ��p���܂��傤�B�����A�O�����C�𗘗p�����ꍇ�A���C���e�ɂ��Ă̕����߂�悤�ɂ��Ȃ��ƁA�������ŏI����Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ŁA���̓_���ӂ��K�v�ł��B
���@30���~�����̔��i�̍w��
����A10���~�ȏ��1�N�ȏ�g�p�ł���̂��͎̂��Y�v�シ��K�v������܂����A������Ƃ̓���ŁA10���~�ȏ�30���~�����̎��Y�̍��v�z���A300���~�����܂łɂ��āA�S�z��p�����ł��܂��B���Z���܂łɃp�\�R����30���~�����̕K�v�Ȕ��i���w������̂��ߐłƂȂ�܂��B
���@�Г����s�̎��{
���]�ƈ��̉ߔ������Q�����A4��5���܂ł̗��s�ŁA�Љ�ʔO�㑊���ƔF�߂���͈͂ł���ΑS�z�o��Ƃ��ĔF�߂��܂��B�������A�s�Q���҂ւ̌����x����A�����݂̂̎Q���A����̏]�ƈ��݂̂̎Q���̏ꍇ�́A�ܗ^�Ƃ��ĔF�肳��܂��B
���@���Z�ܗ^�̎x��
�����Z�ɂ����āA��N�ȏ�̗��v�������߂�ꍇ�A�]�ƈ��ւ̊��ӂ̋C�����������ɕ\���Ӗ��ŁA���Z�ܗ^���x������̂��������Ƃł���܂��B�����A���N�x�����Ă���ƁA�]�ƈ��͓�����O�Ƃ����C�����i�x�����������Ȃ�O�i�K�Ō��Z�ܗ^�Ăɂ��Ă��܂��Ă��܂��j�ɂȂ��Ă��܂��A�x���ł��Ȃ������Ƃ��ɁA�]�ƈ��̕s�����\���\��������̂ŁA�x�����͂悭�������Ďx������悤�ɂ��ĉ������B
���@�|�Y�h�~���ςւ̉���
�|�Y�h�~���ς͓��Ӑ悪�|�Y�����ꍇ�A�|������10�{�܂Ŏ����̗Z�������Ă��炦�鐧�x�ł���܂��B��ړI�͓|�Y���̗Z���ł����A�|�������S�z��p�ƂȂ邽�߁A�ߐŖړI�œ|�Y�h�~���ς։�������̂���ł���܂��B���z20���~�̊|�����̂��߁A12�����O�[���s���A240���~���Z���܂łɎx�o����A240���~��p�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B�|�����̏����800���~�ł���A40�����ȏ�o�߂���A���800���~�߂��Ă��炦�܂��B�߂����ꍇ�͎G�����ƂȂ�܂��̂ŁA�ސE�����̎x�o������Ƃ��ɉ��Ƃ悢�Ǝv���܂��B
���@�ܗ^�������v��̌���
���Z���܂łɎx���ґS���ɒʒm���s���A���Z���ȍ~1�����ȓ��Ɏx������ꍇ�A���Z�ɂ����đS�z�ܗ^�������̌v�オ�F�߂��܂��B�Ŗ����������ӎ����āA�ʒm�ɂ��ẮA�]�ƈ��̏�������������Ă����Ƃ悢�ł��傤�B
���L�̓��e�͎x�o��Ȃ������ł����A��Ў��Y�̏��ł��Ӗ����鎖���ł��̂ŁA�{���ɕs�v�ƂȂ����ꍇ�Ɏ��s����悤�ɂ��ĉ������B
���@�s�v�ȌŒ莑�Y�̏��p�┄�p�̎��{
�s�v�ȌŒ莑�Y�ɂ��ẮA�ꏊ������Ă��邱�Ƃ��珈�����������܂��傤�B���p�ł�����̂͌��Z���܂łɔ��p���s���A���p�ł��Ȃ����̂́A�X�N���b�v�Ƃ��Ĉ�������Ă��炢�܂��傤�B���݁A�X�N���b�v���l���㏸���Ă��܂��̂ŁA�Ԉ���Ă��В��̃|�P�b�g�ɓ���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������i�ŋ߂̐Ŗ������ł悭���Ă��܂��j�B�X�N���b�v�����������Ƃ��ؖ����鏑�ނ�ʐ^����K���ۊǂ��Ă����Ă��������B
���@���������ޗ��E���i���̔p������
�����ł��Ȃ��ޗ��⏤�i���ɂ��ẮA���Z���܂łɔp���������������܂��傤�B�p����������ꍇ�A�p���������Ƃ��ؖ����鏑�ނ�K���ۊǂ��Ă����Ă��������B
���Ӑ�̓|�Y���ŕs�Ǎ����c���Ă���ꍇ�A���Y�������Ŕz�����̌����ݏꂠ��ꍇ�́A�ŏI�z���܂�50���̑ݓ|�������̌v��̂܂܂ł����A����̍������e���疾�炩�ɔz�����������߂Ȃ��ꍇ�i��s���̗D��������Y���������ꍇ�j�A���Z���܂łɊǍ��l�ɍ������̒ʒm������e�ؖ��ŏo���܂��傤�B����ɂ���āA�s�Ǎ��S�z���ݓ|�����Ƃ��Ĕ�p�����ł��܂��B
|
���Z����ɍs���邱��
|
�|�C���g�F����Ȃ��K���Ȍo����v�サ�܂��傤
���@�Y��̎d����������Ȃ��v�コ��Ă��܂����H
���Ђ̎d�����̒��ߓ����A���Z���ƈ�v���Ă��Ȃ��ꍇ�́A���ߓ��̗������猈�Z���܂łɔ[�i���ꂽ���̂��K���Ɍv�コ��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B
���@�Y��̋���������Ȃ��v�コ��Ă��܂����H
�����̒��ߓ������Z���ƈ�v���Ă��Ȃ��ꍇ�́A���ߓ��̗������猈�Z���܂ł̊��ԂɑΉ����鋋�����v�コ��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B�ʏ�A1������������ňĕ�������@�Ŗ����v����s���܂��B
�i���j���������s���ꍇ�A������V�̕����ɂ��Ă͓������͓K�p�ł��܂���B������V�͌ٗp�_��ł͂Ȃ��ϑ��_��̂��ߓ������Ƃ����T�O�����݂��Ȃ�����ł��B
���@�����������A�J�[�h���ςȂǂ���Ȃ��v�コ��Ă��܂����H
������������J�[�h���ς͎��ۂ̗��p���ƈ���������2�������炢�̃Y����������\��������܂��̂ŁA���Z���܂ł̗��p�����K���Ɍv�コ��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B�������ɏ�����Ă��鐿�����Ǝ��ۂ̗��p�����قȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���ۂ̖��ׂŊm�F���Ă��������B
���@�Œ莑�Y�ł̖����v�オ�s���Ă��܂����H
���莑�Y�ł̎x�����͒ʏ�4���ɕ����Ďx�����܂����A4�������ׂČv�コ��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B���Z����12��������3�����܂ł̉�Ђł͓K�p�͂���܂���B�ʏ�4���ɕ��ی��肳��܂��̂ł��̎��_�Ŗ����v�オ�\�ƂȂ�܂��B�[����4���`12����4��������܂��̂ŁA���Z���ɂ����Ė��[�����ɂ��Ė����v�オ�\�ƂȂ�܂��B
���@�Љ�ی����̖����v�オ�s���Ă��܂����H
����A�Љ�ی����̉�Е��S���͖����v�オ�\�ƂȂ�܂��B�����Ɉ��������Љ�ی����͑O�����̂��߁A���Z���̕��͗����������ƂȂ�܂��̂ŁA�����v�オ�\�ł���܂��B�܂��A�������x���̏ꍇ�́A�������߂̈������ƂȂ�܂��̂ŁA���������z�������v�コ��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B
���@�Œ莑�Y���p�����K���Ɍv�コ��Ă��܂����H
�p�����������Œ莑�Y�ɂ��ď��p�����v�コ��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B
���@�~��������ŕԊ҂���Ȃ����̂́A�K���ɔ�p��������Ă��܂����H
���҂���Ȃ��~������5�N�i�X�V���̎x����������ꍇ�͒��݊��ԁj�ŋϓ����p����Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B�܂��A�����͋����Ő��N��ƒ��ɏ[�������_��̏ꍇ�A�K���ɉƒ��Ƃ��Čo�������Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B
�|�C���g�F�Ŗ������b�g�̂���Ŗ@��ϋɓI�ɁA���A�K���Ɋ��p���܂��傤
���@���̋@�B�����w�������ꍇ�Ŋz�T�����͊������p�̓K�p���Ă��܂����H
������Ǝҁi���{����1���~�ȉ��j������24�N3��31���܂łɁA160���~�ȏ�̋@�B���A120���ȏ�̏��@�퓙�A�\�t�g�E�F�A�̑��w���z70���~�ȏ���w�������ꍇ�A���{����3000���~�ȉ��̖@�l�́A7���̐Ŋz�T���i�@�l�ł�20��������A1�N�ԌJ�z���\�j�𗘗p���邱�Ƃ��\�ł���A���{����3000���~���̏ꍇ��30���̊������p�̂ݑI���ł��܂��B
�������p�͏��p�z��O�|���Ōv��ł��邾���ŁA���p�z�̑��z�͓������ߌ��Ŋz�̓[���Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA���{��3000���~�ȉ��̖@�l�́A7���̐Ŋz�T���𗘗p���܂��傤�B
���@����P�������s���Ă���ꍇ�A�Ŋz�T���̓K�p���Ă��܂����H
����23�N3��31���܂łɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ����āA���J����ɑ��鋳��P����p�̊�����0.15���ȏ�̏ꍇ�A����P����p��8���`12���̋��z���Ŋz�T���i�@�l�Ŋz��20��������j�ƂȂ�܂��B
���@���H�̐ڑҌ��۔�ɂ��Ĉ�l������5,000�~�����̂��̂��敪���Ă��܂����H
���H�̐ڑҌ��۔�ɂ��Ĉ�l������5,000�~�����̏ꍇ�A�Ŗ���A���۔�Ɋ܂܂�܂���̂ŁA�S�z�o��Ƃ��ĔF�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B���۔�͌���A600���~�܂ł�10�����o��Ƃ��ĔF�߂�ꂸ�A600���~���������͑S�z��p�Ƃ��ĔF�߂��܂���B
��l������5,000�~�����̌��۔�ɂ��Ă̗v���́A�@���H�Ɋւ���x�o�ł���A��ЊO���̐l���K�����Ȃ���B����ɐ���̉�Ж��Ǝ����L�����l����������悤�ɂ���
���@�������p��K���Ɍv�Z����Ă��܂����H
����A10���~�ȏ��1�N�ȏ�g�p�ł���̂��͎̂��Y�v�シ��K�v������܂����A������Ƃ̓���ŁA����24�N3��31���܂łɎ��Ƃ̗p�ɋ������ꍇ�A10���~�ȏ�30���~�����̎��Y�̍��v�z���A300���~�����܂łɂ��āA�S�z��p�����ł��܂��B
|
�o�c�҂̐ߐő�
|
���@���K�͊�Ƌ��ς̉���
�o�c�Җ{�l�̑ސE�����̂��߂ŁA�������z�i���7���~�j���|�����Ƃ��ċ��o������̂ł���܂��B�|�����́A�S�z�{�l�̏�������T������邽�߁A�����ŋy�яZ���ł����łƂȂ�܂��B65�Έȏ��15�N�ȏ�|���Ă���ꍇ�A���ϋ�B���x������܂��i���S�E�p�Ɠ��̋��ϋ�A���͏��Ȃ��j�B�x���z�͑ސE�����Ƃ��ĉېł���邽�߁A����ł͂��Ȃ�Ⴂ�Ŋz�ƂȂ�܂��B
�������i���A�펞�g�p����]�ƈ���20���ȉ��i���ƂƃT�[�r�X�Ƃ�5���ȉ��j�̏ꍇ�̖����݂̂ł���܂��B�ݗ����Ă����̉����������߂��܂��B
���@�m�苒�o�^�N���̉���
���ƔN����������݂��Ȃ���Ƃɂ����āA�������z�i���2��3��~�j���|�����Ƃ��ċ��o������̂ł���܂��B�|�����͑S�z�{�l�̏�������T������邽�߁A�����łƏZ���ł����łƂȂ�܂��B�^�p�͎����ōs���A�^�p���ʂɂ���ď����̔N���̎x���z�͕ϓ����܂��B
���@���Њ��̑��^
���N�A���Њ��ɂ��đ����Ŕ�ېŘg�ł���110���~�܂ł̊������q���⑷�ɑ��^���s���܂��B
���j�쐬�����݂̖@�ߓ��Ɋ�Â��č쐬���Ă���܂��B
�@�@�K�p�ɓ������ẮA�K���ŗ��m���̐��Ƃɂ����k���������B